非認知能力について
非認知能力とは
非認知能力とは、知能検査や学力検査では測定できない能力を意味しています。
具体的には、やる気、忍耐力、協調性、自制心など、人の心や社会に関係する力です。
自分を動機づけて高めようとしたり、自分の感情をコントロールしたりしながら、
自分と他者を大切にできる非認知能力の育成が、変化の激しい社会のなかで求められています。
非認知能力は、個人差は大きいものの、特に1歳頃から5〜6歳頃の「幼児期」に著しく発達するとされます。
また学童期や思春期にも非認知能力が発達していき、さらに大人になった後も非認知能力は伸ばすことが可能だと
考えられています。
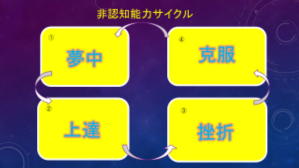
◆自己にかかわる力
興味をもったことに対して、積極的に挑戦する。
疑問に思ったことは、自分で調べようとする。
自分の能力や価値を信じている。
周囲の人の意見に流されず、自分の信念を貫く。
◆社会性にかかわる力
友達と協力して遊んだり、活動したりする。
意見が対立しても、互いに尊重し、話し合いをする。
周りの人の気持ちに共感し、思いやりを持って接する。
約束を守る。
◆セルフコントロール
美しいものや感動的なものに対して、心動かせれる。
困難な状況でも、諦めずに取り組む。
目標達成のために、努力を続けることができる。
失敗から学ぶことができる。
子どもの非認知能力を育てるために避けるべき行動
◆子どもを他人と比較する
「あの子はもう○○できるよ」「○○くんは上手だったのに」など、他人と比較するような発言をしていると、子どもは
劣等感を抱いてしまう可能性があります。自信を失い、自己肯定感が下がることにも関係してくるため比較するのは
避けましょう。
◆挑戦に口出しをたくさんする
子どもがやる気を持ってチャレンジしていることに口を出しすぎると、子どもが萎縮してしまいます。大人が思う以上に
子どもは敏感です。親の顔を見て行動するようになり、子どもがやりたいと思ったことができなくなると能力を伸ばすことが
難しくなります。いろいろと心配になることがあっても、子どもの成長のために細かい点は気にせず、静かに見守りましょう。
◆子どもの失敗を防ぐために動く
失敗すると子どもががっかりするから、と思って親が子どもの失敗を防ぐために動いてしまうと、失敗から学ぶことができなくなります。「失敗はいけないことではない」「改善策を考えられる」「失敗する可能性を考え、予測が立てられるようになる」「失敗してもやり直せる」などの認識をもつことが大切です。失敗も経験になるため、子どもがやりたい気持ちを持っているときは自由に挑戦させましょう。